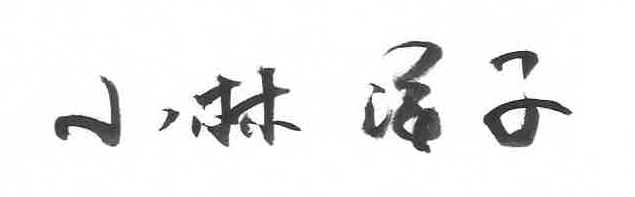小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
本日は、私の4年間の市政運営に当たりましての所信を表明する機会をいただきましたことに感謝を申し上げます。
議員各位におかれましては、小平市の発展と市民の幸せのため、日夜ご尽力されていることに対し、心から敬意を表するものでございます。
このたび、多くの市民の皆様のご支援をいただき、2期目の市政運営を担わせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに、市政運営に当たっての基本姿勢について、申し上げます。
小平市の将来人口推計をみると、今後は少子高齢化や人口減少が進みます。財政状況も厳しくなることが想定されますが、さまざまな課題と向き合い、市民の皆様が「小平市に住んでいてよかった」と思えるまちづくりを推進し、小平市の将来像「つながり、共に創るまち こだいら」の実現に向けて、着実に歩みを進めてまいります。
そのためにまず必要なことは、物価高対策です。これまでも、国や東京都、小平商工会と連携し、4年間で159億円の支援を実施してきました。今後も、家庭用防犯カメラなどの購入費の補助、事業者物価高騰応援金などの支援を実施し、市民生活・市内経済を守ることを第一に考え、困窮する市民や明日に不安を抱える事業者に寄り添い、市民の命と暮らしを守るための市政運営に努めてまいります。
また、少子化の進行は深刻さを増しています。国が公表している最新の全国出生数の確定数は、72万7千277人で過去最低となりました。このまま少子化が続けば、労働人口が減少し経済活動を衰退させるばかりでなく、何よりも地域の、そして社会全体の活力が失われかねません。
そのような危機的な状況の下、政府は、希望する若者がこどもを持ち、安心して子育てできる社会の実現を目指し、少子化の流れを食い止めるための取組を強化する方針を打ち出しています。また、東京都においても、「東京都の少子化対策2025」を表明し、取組を進めています。こうした中、「子育て・教育で選ばれる小平」の実現に向け、子育て施策を積極的に推進してまいります。
大きな時代の転換期にあるからこそ、子育て、教育、福祉、まちづくり、政治や行政のしくみも含め、時代に合わせて変えていく必要があり、積極果敢に「市民の幸せ」のために邁進していく所存でございます。
次に、具体的な政策について述べさせていただきます。
公約として掲げました7つの約束を柱とし、重点的に推進してまいります。
1期目の任期中に、避難所運営マニュアルがすべての小中学校等の避難所に整備されました。今後は、このマニュアルを活用した避難訓練を実施し、マニュアルをブラッシュアップしてまいります。
また、在宅避難の準備を進めていただき、自助の備えを講じている市民の割合を高めるとともに、共助・公助の取組も進めます。
併せて、マンション防災における自助・共助を推進し、ペットの同行避難訓練についても実施してまいります。
安全で安心なまちであることは、市民の共通の願いです。昨今の特殊詐欺や訪問型の詐欺被害など市民に不安感が広がる中、カメラ付きインターホン等の防犯機器の購入費助成などにより、住まいの安全安心の確保に努めるとともに、小平警察署と連携し特殊詐欺と闇バイトの撲滅に取り組みます。
DXは加速度をつけて取り組んでいかなくてはならない課題です。
今後、急速な人口減少が見込まれる中、自治体が持続可能な行政運営を行うためには、自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、AI等の活用により業務効率化を図り、人的資源を有効に配置して、行政サービスのさらなる向上につなげていくことが求められます。DXを推進するに当たっては、市民の皆様にその意義を共有しながら進めていくことも重要です。
まずはペーパレス、はんこレス、FAXレス、キャッシュレスと4つのレスに取り組むとともに、AIやSNSを活用し、子育て支援にもデジタルを取り入れてまいります。そして、高齢者へのデジタルデバイド対策として、スマートフォンの使い方講座などの支援を充実させます。DXの推進とマイナンバーカードの利用で、待たない・書かない市役所、市役所に行かなくても手続きがデジタルで完結できる 行かない市役所にしていくことを通じて、人にやさしいDXを進めてまいります。
本年11月には第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025が開催されます。
日本では初めての開催であり、また1924年にパリで第1回デフリンピックが開催されてから、100周年の記念となる大会になります。デフリンピックを契機にデフスポーツや、ろう者文化への理解促進が図られるよう努めてまいります。
また、障がいのある方や高齢者、外国人など、市民一人ひとりが安心して暮らせるよう、多様性を尊重し、包括的な支援体制を整備いたします。そして地域のつながりと誰もが輝ける取組として、高齢者の活動支援や居場所づくり、外出支援をすることで健康長寿のまちにしてまいります。
さらに困りごとの解決のため、ヤングケアラー支援、居住支援、おひとり様終活支援を進めるとともに、庁内では障がい者優先調達推進法に基づく取り組みを進めます。
様々な取組を進める中で、より幅広く効果的に、多様な意見を聴く仕組みをつくります。
子育てを取り巻く環境については、核家族化・共働き世帯増加などの家族構成の変化、地域のつながりの希薄化などにより親族や友人からの支援を受けづらい環境に置かれており、孤立感や不安感を抱えながら子育てを行っている現状があります。そうした家庭を地域で支えていくことは非常に重要であり、朝や放課後等、こどもの居場所づくりを充実してまいります。また、幼稚園や保育園などの幼児教育・保育施設と小学校が連携して、こどもの生活や学びを円滑に接続することを目指す幼保小連携を充実し、小1プロブレムの解決に取り組みます。さらに、生成AIの活用やDXの推進で教員の働き方改革を進めます。
小・中学校の通常の学級においては、発達障がいの可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童・生徒は8.8%ほどの割合で在籍していることが明らかになっています。同時に、それ以外にも学習面や行動面で何らかの困難を抱える児童・生徒もいることから、すべての学校・学級において、これらの児童・生徒に対する支援が、喫緊の課題となっています。
そのため、教育委員会と連携して、通常の学級において、学習面や行動面で何らかの困難を抱える児童・生徒に対して、学習支援、生活支援等の体制の整備や、指導方法の改善等を行う研究・研修体制を構築するなど、教育の場で個に応じた児童・生徒等の支援を進めます。
その他、不登校の児童・生徒に対する学校以外の場での学習等の支援の充実は、これからますます必要になってまいります。個々の児童・生徒の状況に応じた環境づくりのため、フリースクール等と連携した不登校支援を進めます。
また、物価高騰は子育て世代の生活を圧迫しており、家計や教育費に大きな影響を与えています。学校給食費の無償化の継続と、家計の教育費の負担軽減をしてまいります。
これまでも、市民の声を活かして公共施設マネジメントに取り組んでまいりました。引き続き、情報提供についてはわかりやすく、また動画なども活用しながら市民が知りたい情報を得られるよう取り組んでまいります。
市内には西武鉄道の路線も多くあります。小平のまちづくりを考えていく上では、西武鉄道株式会社との連携は必須であり、市民の利便性や安全性などの点からも道路と鉄道の立体化や、ホームドア整備について連携していくとともに、市内から羽田空港へのアクセス改善などにも取り組んでまいります。
また、公園トイレが清潔で快適であることは、公園利用者の利便性等の向上だけでなく、公園そのもの、さらにはまちの大きなイメージアップにつながる重要なポイントです。改修などを効果的に行うことで快適で清潔なトイレづくりを順次進めます。
近年は、後継者が見つからないことで、事業が黒字でも廃業を選択する企業が多いといわれています。中小企業の廃業理由のおおむね3割が後継者難という調査の結果もあり、今後、後継者不足が地域の経済に大きな影響を与えることは明らかです。
地域で長く育まれてきた店舗が失われることは、地域の魅力の減退につながり、様々な分野に影響が出ることも懸念されます。後継者の不在は、事業主が一人で考える問題ではなく、地域全体の問題と捉え、持続可能な地域づくりのために市として積極的に関わっていく必要があります
併せて、街の魅力を高めるシティプロモーションを強化し、戦略的広報を進めるとともに、企業・大学・研究機関等と連携したスタートアップ支援等の公民連携デスクを設置いたします。
また、市内にある各種スポーツ団体と連携し、スポーツやイベント等の開催により市の活性化に取り組みます。
さらに、公契約の適正な履行、公共事業 及び公共サービスの品質並びに労働者等の適正な労働条件の確保を図るため、公契約条例の制定を目指します。
いま世界は、国境をまたぐ大気や海洋の汚染、地球温暖化による気候変動など、グローバルな環境問題に直面しています。地球規模の環境問題であっても、その原因が個人の生活・活動に結びついていることを考えると、解決の糸口は一人ひとりの生活の中にあるといえます。
そうした意味でも、市民の生活に一番近い基礎自治体である市が、国の方針や政策を取り入れながら、市民とともに環境問題に取り組んでいく必要があります。
まずは炭素循環社会の達成に向けLED照明や省エネ家電への買換え補助を進めます。そして公共施設への再生可能エネルギー等の導入を進めます。
また、身近な農地を守ること、緑地である公園を整備していくことも大切な取組です。農業者支援や地産地消の推進、学校給食への地場産農産物の導入を促進し、小平の農業を守ります。そして鷹の台公園、鎌倉公園など公園づくりを通して、人がつながり、公園を起点としたコミュニティづくりを進めてまいります。
以上が、市の目指す将来像「つながり、共に創るまち こだいら」の実現に向けて、重点的に推進していく具体的な政策です。
私が大切にしているのは、「実行力」と「スピード」です。
これまでの4年間、そしてこれからの4年間も、実績と挑戦の積み重ねで、未来の小平をともに創っていきましょう。
結びに、物価高騰、気候変動危機、人口減少など、私たちは今、まさに激動する時代の真っただ中にあります。経営学者のピーター・ドラッカーは「まず何よりも、変化を脅威ではなく機会としてとらえなければならない」と説きました。私たちはこの局面を何よりのチャンスと前向きに捉えることが重要です。
大胆かつ戦略的に政策を展開していくことで、社会の新たな景色をつくりあげていかなければなりません。誰もが生きがいを感じ、自分らしく暮らしていける小平の実現に向けて、スタートダッシュを切るべく、全力で市政の舵取りをしてまいります。
議員各位をはじめ、市民の皆様のご理解とご協力をいただくとともに、国や東京都など関係機関との連携をさらに深め、応援もいただきながら、市民に寄り添った施策を職員とともに全力で推進してまいります。
議員各位におかれましては、ご指導とお力添えをいただきますよう心からお願い申し上げまして、私の所信表明とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。